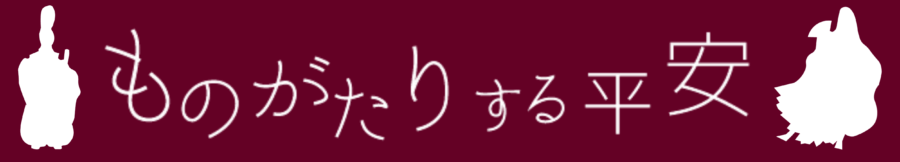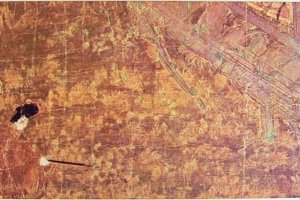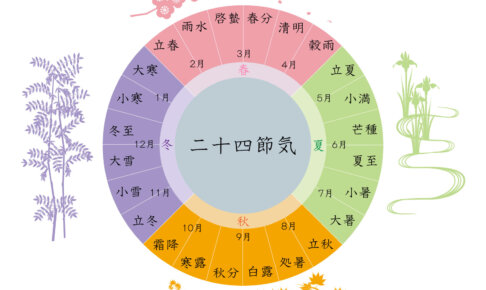ほととぎすの声を聞きに出かけ歌を詠むのを忘れて帰ってきた清少納言を定子様がたしなめるという『枕草子』のエピソードを以前紹介しました。
上の記事で最後に少しだけ触れているのですが、実は清少納言は和歌を詠むのがあまり得意ではないのです。
そうはいっても、清少納言は勅撰集にも和歌が入集していますし、「小倉百人一首」にも和歌がとられています。同じ女性の歌人なら例えば伊勢や小野小町には歌人としての知名度で劣るかもしれませんが、第三者から見て下手ということはないですよね。むしろ、漢詩の知識を活かした技巧など、『枕草子』に登場する和歌には優れたものも多いのです。
しかし清少納言は「私は和歌が苦手」と自認していたのです。今回は、清少納言と和歌の才能についてのエピソードを『枕草子』から紹介します。
清少納言が和歌を詠みたくない理由とは?
上で紹介した記事の中で、清少納言は定子様に「さっさと歌を詠んでしまいなさい」と言われてもなお、別の人に押し付けようとするなど、その役目から逃れたい心情について少し触れています。
同じ「五月の御精進のほど」の段の続きで、清少納言は歌を詠みたくない理由をこのように語っています。
「何か。この歌よみはべらじとなむ思ひはべるを。物のをりなど、人のよみはべらむにも、『よめ』など仰せられば、え候ふまじき心地なむしはべる。いといかがは、文字の数知らず、春は冬の歌、秋は梅、花の歌などをよむやうははべらむ。なれど、歌よむと言はれし末々は、すこし人よりまさりて、『そのをりの歌は、これこそありけれ。さは言へど、それが子なれば』など言はればこそ、かひある心地もしはべらめ。つゆとりわきたる方もなくて、さすがに歌がましう、われはと思へるさまに、最初によみ出ではべらむ、亡き人のためにもいとほしうはべる」
『枕草子』「五月の御精進のほど」(校注・訳:松尾聰・永井和子『新編日本古典文学全集』/小学館)より
訳すと、
「いえもう、私はこの歌というものを一切詠みますまいと思っているのですが、何かの折に他の人が詠むにつけて『あなたも詠みなさい』などと仰せになるのでしたら、私はもうおそばに伺候するのも続けられそうにないという気持ちがします」
「私だって、歌の字数もわきまえずに、春に冬の歌を詠んだり、秋に梅や桜の花を詠むなんて、そんなめちゃくちゃなことはいたしません」
「歌詠みの子孫(※清少納言の父は清原元輔、祖父は清原深養父)は、少しでも人より優っていれば『この歌はすばらしい。何といっても誰それの子だから』と言われるならそれほど誇らしいことはないでしょうけれども、私のように少しも人より際立つところもなく、もっともらしくいかにも歌ですといった得意顔で歌を披露しては、亡き父にも気の毒なことです」
と、こういうわけがあったのです。
優れた歌人の娘だからこそ謙虚に
清少納言は祖父、父と続けて優れた歌人を輩出した家の出身。清少納言自身、さすがにとんでもない歌を詠むとは思っていないものの、父や祖父のように飛びぬけて才能があるわけではない……。
優れた歌人を父に持つからこそ、平凡な自分の歌に謙虚な姿勢でいるのです。もしかしたら、「元輔の娘だ」ということで人から過度な期待をされた経験が何度もあったのかもしれません。
清少納言も「親の七光りだ」といわれるのは嫌だったでしょう。定子のもとで仕えることになったのもおそらく元輔の娘だったからでしょうが、それはそれとして……。漢詩の知識やものを見る感性など、清少納言には歌以外に秀でた才能がありますから。
定子の反応は
この清少納言の話を聞いた定子は、笑って「それならお前の心に任せましょう。私の方では『詠め』とも言いますまい」と、主人から「詠まなくていいよ」とお許しが出たのです。
これで清少納言は一安心。咄嗟に歌を詠む必要がなくなり、「気が楽になりました!もう今は歌のことを気にかけないようにします」と胸をなでおろすのでした。
やっぱり人から「詠め」と言われるけど
しかし、宴の場では歌は必須。内大臣(定子の兄の伊周)もいる宴の場で清少納言が歌を詠まないでいるのを不思議に思われてしまいます。
「詠め、詠め」と責め立てる伊周。それでも清少納言は「お許しが出たので、歌を考えてもいません」ときっぱり断るのです。
様子を見ていた定子は、清少納言にこんな歌を投げて渡します。
元輔が後といはるる君しもや今宵の歌にはづれてはをる
『枕草子』「五月の御精進のほど」(校注・訳:松尾聰・永井和子『新編日本古典文学全集』/小学館)より
「元輔の子と言われるお前が、今宵の歌に加わらないでかしこまっているの?」とからかう内容。清少納言の返事は、
その人の後といはれぬ身なりせば今宵の歌をまづぞよままし
『枕草子』「五月の御精進のほど」(校注・訳:松尾聰・永井和子『新編日本古典文学全集』/小学館)より
「もし私が誰それの子だと言われない立場だったら、今宵の歌を真っ先に詠んだでしょうに」
というものでした。
偉大な父を持つプレッシャー
「もし父が元輔でなかったら、何も気にせず自由に歌を詠んだでしょうに」。上の歌にはそんな意味もあるでしょう。平安の二大文学作品とされる『枕草子』の作者たる清少納言でも、こと歌に関しては偉大な父のあとで、大変なプレッシャーを感じていたはずです。
ここで定子に「詠まなくてもいい」と許可をもらいましたが、もちろん中宮に仕える女房として歌のひとつも詠まないでいる、そんなことは許されません。この先も何かにつけて歌を詠まなければならないシーンが何度もあったでしょうね。
この「五月の御精進のほど」のエピソードは、『後撰和歌集』の撰者である元輔を父に持つ清少納言が自分の歌の才能をどのように感じていたのかがわかる貴重な資料といえるでしょう。