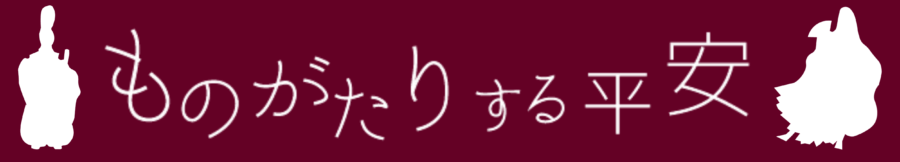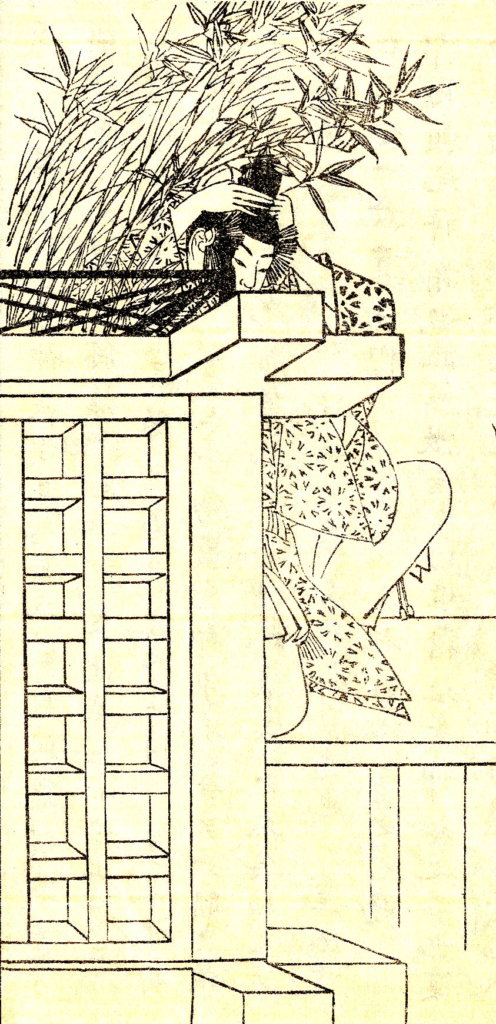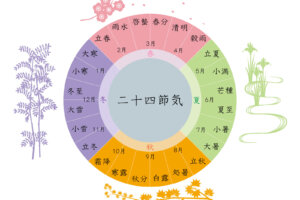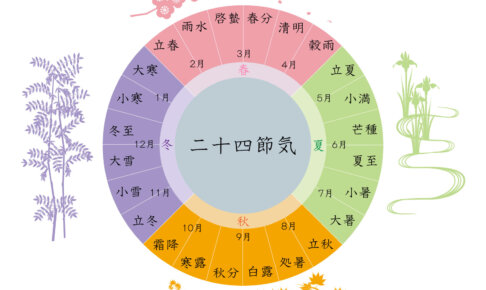現代の場合、室内で帽子を被っていると無礼にあたる、マナー違反だというのが常識ですよね。でも、平安貴族は逆でした。室内であっても野外であっても、男性が頭髪を露にするのはとても恥ずかしいことだったのです。
どこまで恥ずかしいかというと、ふんどし姿になるのとどっちが嫌か?というくらい。
どんな場でも冠や烏帽子が欠かせないアイテム
平安時代の男性貴族のファッションをちょっと見てみましょう。
まずはこちら、出仕する際の服装「束帯(そくたい)」です。
貴族(主に公卿や殿上人)が宮中へ出仕する時の服装で、第一礼服にあたります。例えるなら、ビジネススーツというよりもっと上等な、冠婚葬祭で仕えるフォーマルウェアというところでしょうか。燕尾服のほうが近いかもしれません。束帯姿では冠を被るのが決まりです。
続いては、武官の束帯。上の束帯は文官スタイルです。
こちらでも冠を被るのが決まり。このイラストにはありませんが、冠には纓(えい)というものが後ろにのびていて、通常はそのまま垂らしておくのですが、武官の場合は動くときに邪魔にならないよう巻いておきます。
最後は、オフの服装「狩衣(かりぎぬ)」です。
狩衣はカジュアルな普段着です。外で着用することが多いですね。家でくつろぐ際はこれとは別の直衣を着用しますが、烏帽子を被るのは共通しています。
このように、ビジネスなどの公的な場では冠を、私的な場では烏帽子を被るのが男性のマナーでした。貴族だけでなく庶民も同じですし、たとえ家でボーっとしている時でも帽子は脱がないというのが常識だったのです。
冠を誤って落としてしまった!
そうはいっても、ちょっとミスをして冠を落としてしまうことだってあります。誰にだって間違いやミスはあります。冠を落としてしまった人のエピソードも残っているので、2つ紹介しましょう。
落馬して禿げ頭を晒した清原元輔
清原元輔(きよはらのもとすけ)。歌人として名の知れた『後撰和歌集』の撰者のひとりで、清少納言の父にあたる人物です。
この元輔が、ある年の賀茂祭(葵祭)で奉幣使(ほうへいし)を務めたときのこと。元輔は誤って落馬し、冠を落としてしまいました。全く意図しなかったことです。
しかも、このとき元輔はかなり年老いていて、頭髪は禿げ上がっていたとか。この出来事を書いた『宇治拾遺物語』によれば、「髻結なし」つまり、もとどりが全然ないのです。髪を結うほどもなかった、つるつるの頭だったのです。冠を落とすことだけでも恥ずかしいのに、禿げ頭まで晒して……元輔は二重に恥をかいてしまったのでした。
こういうとき、普通の人ならサッと冠を被り直して恥ずかしそうにするのかもしれませんが、元輔は違いました。様子を見て笑った人々に向かっていちいち説明して回ったのです。
「あな騒がし。しばし待て。君達に聞ゆべき事あり」とて、殿上人どもの車の前に歩み寄る。日のさしたるに頭きらきらとして、いみじう見苦し。大路の者、市をなして笑ひののしる事限りなし。(中略)
「君達、この馬より落ちて冠落したるをば、おこなりとや思ひ給ふ。しか思ひ給ふまじ。その故は、心ばせある人だにも、物につまづき倒るる事は常の事なり。まして馬は心あるものにあらず。この大路はいみじう石高し。馬は口を張りたれば、歩まんと思ふだに歩まれず。と引きかう引き、くるめかせば、倒れん(中略)また冠の落つる事は、物して結ふものにあらず、髪をよくかき入れたるにとらへらるるものなり。それに鬢は失せにたれば、ひたぶるになし。(後略)……」
『宇治拾遺物語』巻13「元輔落馬の事」(校注・訳:小林保治・増古和子『新編日本古典文学全集』/小学館)より
とても長いので本文はところどころ省略しますが、元輔は笑って馬鹿にする公達らのところへ歩み寄り、「あなたたちは落馬して冠を落とした私を間抜けだと思うか。それは間違いですよ。たとえどんな慎重な人間でも物にけっつまずいて転ぶことがあるのに、まして馬ならどうか。その上この道はでこぼこしていて思うように歩けない。それをどうにか歩こうと手綱をあっちへこっちへとやるものだから、馬も倒れてしまったのだ。」
「冠が落ちたのだって、紐で留めているわけでもないし、おまけに私の髪は年のせいで抜けてしまって全くない。だから冠が落ちたからといって冠を恨む筋合いはないのだ、うんぬん……」
と、落馬した理由、冠が落ちた理由を説明して回ったのです。
この間、冠は落としたまま。堂々と言い切った元輔は「冠を取ってくれ」といってようやく冠を被ったのでした。これには人々も大笑い。
元輔はドンと構えて説明することで、恥を笑いに変えたのでした。醜態をさらしたからといって恥じ入るのではなく、人を楽しませるほうへ持っていく。元輔にはそういうユーモアがあったのです。
ユーモアという点では、娘・清少納言の『枕草子』は「をかし」の文学と通じる部分があります。やはり親子なのか、似ているのでしょうね。
藤原実方は口論になって他人の冠を叩き落とした?
平安中期、一条天皇の時代に歌人として活躍した藤原実方(ふじわらのさねかた)。「小倉百人一首」にも歌が取られた、中古三十六歌仙のひとりです。
この実方、ある日藤原行成と口論になってしまい、行成の冠を叩き落としてしまった、という逸話が残っているのです。『十訓抄(じっきんしょう)』や『古事談』に載っているエピソードで、実方はこれが理由で陸奥へ左遷されてしまった、と締めくくられます。
叩き落とされた側の行成はというと、こんなことをされても冷静でいたこと、一部始終を見ていた一条天皇にそれが評価され、蔵人頭に抜擢されて以後出世していったというのです。
ただ、このエピソードは事実とは異なるようで。行成の日記『権記』に記された関連する出来事を見てみると(長徳元年9月27日)、冠を落とされたというようなことは全く書いてないのです。書かれているのは、実方の地方赴任はむしろ昇進であるということ。
実方が行成の冠を叩き落としたことが事実なのか創作なのかはわかりませんが、これが原因で二人の進退が決まったわけではないようです。
しかし「冠を落とした」ことで、落とした側が左遷され、落とされて冷静にしていた側が昇進するとは。冠を落とすことが貴族たちにとっていかに重大な事件だったかがうかがえるエピソードですね。
いつでも冠は被ったままで
平安時代の人々にとって冠は大切なアイテムだったことがわかったと思います。
下半身を晒すのとどちらがより恥ずかしいのか。それはわかりませんが、女性との逢瀬を楽しむ瞬間にも冠は外さない、そういうこともあったようですよ。だとすると、ふんどしよりも手放せないものだったかも……?
平安よりももっと昔、600年ごろには初めて冠位・位階が定められました。「冠位十二階」は紫・青・赤・黄・白・黒の六色を濃淡でさらに二つずつに分け、12の色で位を示した。その色分けが施されたのが冠でしたね。平安時代には冠の色で位を分けることはなくなりましたが、冠はそれほど重要なものだったということがわかります。